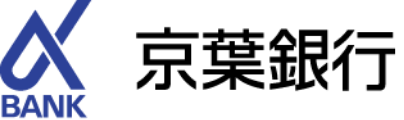ショーウィンドーギャラリー
2022年4月~2022年9月
「優」
優
-
彩りいろどりガラス細工(千葉県)
-
趣きおもむき丸亀うちわ(香川県)
・草木染め(山形県) -
味わいあじわい宮島細工(広島県)
・木べら(長野県) -
装いよそおい広瀬絣(島根県)
・久留米絣(福岡県)
彩りいろどり
ガラス細工(千葉県)
日本のガラス文化の新しい幕開けは、16世紀、キリスト教の伝来と共に始まり、全国へ広まっていきました。
天然素材から生まれるガラスは、約1400℃で溶け、約600℃で冷え固まります。その間、ガラスが最高に美しくなる一瞬を捉えてカタチにしていきます。ガラスの特性を最大限に引き出すため、「ガラスの声」に耳をかたむけ、厚み、重さを数ミリ、数グラムの単位で調整する経験と技術が必要とされます。
ガラス工芸品は、継承され、革新されていく技術と、想像力、好奇心によって生まれています。

趣きおもむき
丸亀うちわ(香川県)
江戸時代初期に金毘羅参りの土産として考案されたもので、朱赤地に「丸金」印が入った、渋うちわが始まりとされています。
材料全てが近隣で揃えられ、全47の製造工程のほとんどは職人の手仕事です。 地紙ひとつとっても、破れにくくするため、素材の厚さにより糊の濃度を調節するなど、最高の材料と卓越した職人技の集大成となっています。
うちわの何とも言えない温もりは、気の遠くなるようなこの作業から生まれ、粋を映し出し、ゆるやかに煽ぐ優美な姿となります。
草木染め(山形県)
染色文化の歴史は古く、縄文時代から植物や貝紫などで染色が行われ、飛鳥時代になると中国や朝鮮の染色技術が伝わり、日本の染色は急速に発展しました。
草花を摘み、煮込むなどしてその色素を抽出し糸を染め、色を落ち着かせるために鉱物の力を借りるなど、草木染めには、自然界の恵みが凝縮されています。
現在では、草木染めが施されたアルミ板から、食器や花器などがつくられることもあり、これは世界でもあまり例のない作品です。

味わいあじわい
宮島細工(広島県)
鎌倉時代初期に神社や寺を建てるために各地から宮大工や指物師などの匠が招かれ、木工技術が伝わりました。
豊富な森林資源に恵まれ、木材の集積地であることから、材料が入手しやすく、木工細工が発展する好立地となっています。
特徴は、水に濡らしわざと木目を立てさせて磨く丁寧な仕上げが施されていることです。
宮島細工として代表的な杓子は、木目に沿ってつくることで、ご飯に木のにおいが移らず、米粒がつきにくくなっています。
木べら(長野県)
へらは、薄く平たい道具の総称で、日本では縄文時代に土器を使った煮炊きが始まった頃、棒でかき混ぜていたものを、使いやすくするためこの形にしたことが始まりとされています。
この木べらは成型から仕上げまで全ての工程で鉋(かんな)が使われています。刃を入れると木の硬さ、木目の向きが手に伝わることで個々の素性がわかりその木にあった形が生まれます。
あえて濡れた状態で削って成形し、乾いたところで仕上げを施すので木が安定します。薄く、丈夫で驚くほど軽く、プロの料理人も重宝しています。

装いよそおい
広瀬絣(島根県)
1824年、伯耆国(ほうきのこく)米子の絣の染織技術が広瀬に伝わり、その後、織り方、染め方に改良が加えられ盛んになっていきました。
広瀬の大柄、備後の中柄、久留米の小柄といわれるように、広瀬絣の特徴は大柄の絵模様にあり、正藍一色に濃淡を交錯させ、正確に図柄が浮かび出るように織り交ぜられます。1962年、県無形文化財に指定されました。
現在も広瀬町に残る紺屋では、代々受け継いだ藍を守り続け、今も昔と変わらぬ技法で綿糸、麻糸、絹糸が染められています。
久留米絣(福岡県)
久留米絣の優しい風合いを織物に浮かび上がらせる技法は、約200年前、農家での偶然の発見から生み出されました。
30もの工程は非常に緻密で、柄を生み出すために糸束を縛って染色し、染めた糸をまた一本一本の糸にほどき、織ることで一枚の織物ができあがります。手仕事が不要な工程はなく職人の高い技術が必要です。
現在では、伝統的な幾何学模様や藍染めだけでなく、モダンな柄、ポップな色合いの製品も多く作られています。