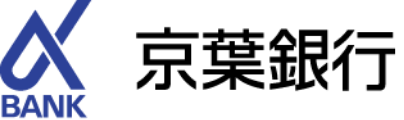ショーウィンドーギャラリー
2021年4月~2021年7月
「颯爽」
颯爽
-
阿波正藍しじら織あわしょうあいしじらおり徳島県
-
京うちわきょううちわ京都府
-
益子焼ましこやき栃木県
-
琉球びんがたりゅうきゅうびんがた沖縄県
-
楊枝ようじ千葉県
阿波正藍しじら織あわしょうあいしじらおり
徳島県
阿波正藍しじら織は、江戸時代に阿波地方で作られていた「たたえ織」という木綿縞(もめんしま)が起源です。明治時代初期、雨で濡れた木綿縞を晴れ間に干したところ、生地が縮みシボという独特の凹凸が生じたことにヒントを得て作られました。
シボがあることで、さらりと肌触りがよく軽くて着やすいため、夏のクールビズ衣料として最適です。
1978年(昭和53年)、国の伝統的工芸品に指定されました。現在ではジーンズや暖簾(のれん)、シャツ、ハンカチなどの多彩なアイテムに活用され、暮らしを豊かに彩っています。

京うちわきょううちわ
京都府
南北朝時代、明(みん)(当時の中国)や朝鮮半島の沿岸地を縄張りとしていた倭寇(わこう)(日本の海賊)によって、朝鮮団扇(うちわ)が西日本に持ち込まれ、紀州から京都へ伝わったのが京うちわの始まりとされています。
江戸時代以降、柄が中骨と一体ではなく、後から取り付けられる、「挿柄(さしえ)」という構造が定着しました。宮廷でも用いられるようになり、土佐派や狩野(かのう)派といった絵師の手により、麗しく優美な彩色が施されるようになりました。
現在も、京うちわは京都の豊かな風土と文化に育まれて発展しており、暑さを和らげるためだけでなく、時代に合わせた新たなデザインが生み出され、おしゃれなインテリアとして楽しめるのも魅力です。

益子焼ましこやき
栃木県
益子焼は江戸時代末期に益子町で誕生し、主に鉢や水がめ、土瓶などの台所用品として生産されていました。当時、益子を治めていた黒羽藩(くろばねはん)の藩主大関増明が殖産事業として援助したことから、鬼怒川を通じて江戸にまで普及しました。その後、生活様式の変化などもあり、日用雑器から民藝品へ用途が移り変わっていきました。
益子焼は陶土に砂気が多く、粘性が少ないことから、厚手に作られ、素朴で温かみのある風合いが特徴です。
現在、約250もの窯元があり、幅広い世代の陶芸作家が多彩な品々を生み出しています。

琉球びんがたりゅうきゅうびんがた
沖縄県
紅型(びんがた)とは南国の空気漂う、華やかに描かれた花鳥風月が特徴の沖縄を代表する染物です。室町時代に諸外国との取引で琉球王朝にもたらされた染色技術が発達し、王族や士族の衣装に取り入れられました。
最大の魅力は、顔料と天然染料を組み合わせ独自の技法で表現されるイルクベー(色配り)です。通常の型染は複数枚の型紙を用いるところ、最後まで1つの型紙を使用しており、また暖色系から黒へ、という色差しの順が決められています。
現在も多くの工房で衣料や雑貨などが生み出されているほか、趣味として自ら体験したり、学ぶ人々も増えています。

楊枝ようじ
千葉県
楊枝は、江戸時代に口内ケア用品として庶民に広まりました。その需要を支えていたのが房総半島の中央部にある久留里産(現在の君津市久留里)の楊枝です。楊枝の材料はクスノキ科のクロモジが使われており、特に君津市のクロモジは日本一香り高いと称されます。
昭和になり機械製の安価な楊枝が普及し始めると、職人が1本1本手作業で作る千葉県産の楊枝は、大量生産品とは一線を画す粋な楊枝として重宝されました。
現在、「雨城(うじょう)楊枝」、「ちば黒文字・肝木房(かんぼくふさ)楊枝」、「畑沢楊枝」等があり、芸術性を活かし装飾品や茶道用品として使われています。