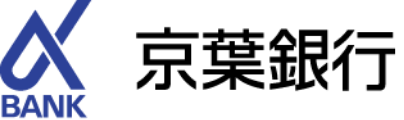ショーウィンドーギャラリー
2020年8月~2020年11月
「共生」
共生
-
三線さんしん沖縄県那覇市など
-
播州毛鉤ばんしゅうけばり兵庫県西脇市
-
奈良筆ならふで奈良県奈良市・大和郡山市
-
高岡漆器たかおかしっき富山県高岡市
-
刷毛はけ千葉県習志野市
三線さんしん
沖縄県那覇市など
室町時代(1300年代後半)、中国福建(ふっけん)から三絃(サンスェン)と呼ばれる楽器が琉球王国に伝わり、のちに三線(三味線)として日本の本土に普及しました。宮廷楽器として発展し、やがて庶民へ伝わり広く愛されていきます。
三線は、黒檀(こくたん)など硬い木材で棹(さお)や胴(チーガ)※を組み、胴にニシキヘビの一枚皮をはって作ります。音色や形がそれぞれ違った代表的な7つの型は、琉球王国時代の名工の名がつけられています。
美しい音色と姿は日本のみならず、世界中の人々も魅了しています。
- ※太鼓部分の木の枠を含む胴全体のこと。

播州毛鉤ばんしゅうけばり
兵庫県西脇市
江戸時代末期(1800年中期)、京都から播州(現在の西脇市)に毛鉤の技術が伝わりました。
毛鉤は雑食性の高い渓流魚が昆虫を捕食する習性から考え出された漁具です。播州毛鉤は、釣る魚の種類や季節、天候、川の流れなどに合わせて、ヤマドリやキジ、クジャク、ニワトリなどの羽根と金銀箔(きんぎんはく)、絹糸、漆などを精巧な細工で組み合わせて、一本ずつ熟練した技で巻きあげて作られます。
500種類ほどある播州毛鉤は、国内毛鉤生産の大部分を占めています。

奈良筆ならふで
奈良県奈良市・大和郡山市
平安時代(800年代)、遣唐使として中国に渡った空海(弘法大師)が大和の国の筆匠(ふでし)、坂名井清川(さかないきよかわ)に製法を伝えたことが奈良筆の始まりとされています。
奈良筆は書く文字によって、鹿や山羊、馬など約10数種の獣毛を使い分け、筆の特徴に合わせて、獣毛の採取時期や体毛の部位による弾力、強弱、長短の違う物を組み合わせて作られます。
筆匠は、伝統の技法「練り混ぜ法※」を駆使し、美しい穂先に仕上げます。
- ※原毛を個別に水にひたして固め、筆の特徴によって配分と寸法を決めて入念に混ぜ合わせる方法

高岡漆器たかおかしっき
富山県高岡市
江戸時代中期(1600年代)、高岡漆器は高岡城築城に伴う町産業として誕生し、漆の上に細工を凝らす「加飾(かしょく)」の技を進化させていきました。
特に、明(みん)時代の漆器を源流とする「勇助塗(ゆうすけぬり)」や漆の粘りを利用して立体感を出す「彫刻塗」、貝殻の細片を組み合わせて文様や絵柄を描く「螺鈿(らでん)」といった技法が有名です。
展示の「青貝塗(あおがいぬり)」は螺鈿(らでん)をさらに洗練させたものです。鮑(あわび)や夜光貝、蝶貝などの貝殻の細片を0.1ミリまで研ぎ出し「貝付け」作業で精密な図案を表現します。漆の表面に、鮮やかに透けて青や虹色に輝く貝特有の美しさを浮かび上がらせています。

刷毛はけ
千葉県習志野市
平安時代(700年代)、刷毛は経本や仏画の巻物の紙の継ぎや裏打ちのために誕生しました。その後、鎌倉時代から室町時代(1300年代)にかけて、襖や障子などの紙貼り用として刷毛が盛んに使われるようになりました。
刷毛は、馬、山羊、狸、鹿等の獣毛を一本ずつ重ねて手作りされます。京型と江戸型があり、表具(ひょうぐ)※1、経師(きょうじ)※2、絵画修復等、用途に合わせて使用します。
東京国立博物館に所蔵されている文化財の修復に使われるなど、日本文化の保存、継承に必要不可欠な道具となっています。
- ※1布や紙を貼り合わせ、巻物・掛軸・屏風・襖などに仕立てること
- ※2書画や屏風・襖などを仕立てること。