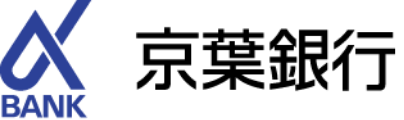ショーウィンドーギャラリー
2019年4月~2019年7月
「光風」
光風にちにちこれこうにち
-
上総角凧かずさかくだこ千葉県指定伝統的工芸品・郷土玩具
千葉県市原市 -
三州鬼瓦工芸品さんしゅうおにがわら
こうげいひん経済産業大臣指定伝統的工芸品
愛知県高浜市 -
東京銀器とうきょうぎんき経済産業大臣指定伝統的工芸品
東京都 -
出石焼いずしやき経済産業大臣指定伝統的工芸品
兵庫県豊岡市 -
甲州印伝こうしゅういんでん経済産業大臣指定伝統的工芸品
山梨県甲府市
上総角凧かずさかくだこ
千葉県指定伝統的工芸品・郷土玩具
千葉県市原市
上総角凧は、江戸時代中期より上総地域に伝わり、各種のお祝い事に用いられてきました。
特に、男子の出生を祝い、元気な子に育つようにとの願いが込められ端午の節句に揚げるという風習があります。
角凧作りは漁師や農家、職人の副業として受け継がれてきました。骨は、2年間寝かせた上総の篠竹(しのだけ)にひごを挽(ひ)き、手漉(てす)き和紙を巻いて組みます。そこに伝統の絵柄として「熊と金太郎」「鯉と金太郎」「武者絵」などを大胆に描いていきます。
凧の上部に取りつけた「うなり※1」は、鯨のヒゲで作られており、このヒゲが風に震えて独特の「うなり音※2」を出します。
昔ながらの知恵が詰まった伝統的な技でつくられた角凧。「うなり音」をあげながら大空を舞う勇姿が目に浮かびます。
- ※1 うなり:凧につけて、風の力で鳴らすもの。
- ※2 うなり音:元気に育つようとの願いが込め、その心意気を表現したものと言われる。

三州鬼瓦工芸品さんしゅうおにがわらこうげいひん
経済産業大臣指定伝統的工芸品
愛知県高浜市
三州瓦は、江戸時代、三河の地でその原料となる良質の三河粘土が採れたことと、海運輸送に適した地の利を生かしたことで、日本三大瓦に発展していきました。
三州鬼瓦は主に西三河地方で作られる屋根の一番高い棟の両端を飾る瓦で、魔除け・厄除け、繁栄や富の象徴として飾られてきました。型紙を使った総手造りや石膏型で粗成形(あらせいけい)し、木べらや金べらで造形します。そして、焼成(しょうせい)後に「燻化(くんか)※」を行い、製品の特徴である「いぶし銀」を発色させます。その職人は鬼師(おにし)、鬼板師(おにいたし)と呼ばれ、粘土の声を聞きながらヘラ一本で魂を込め鬼面(きめん)鬼瓦(おにがわら)を仕上げます。
現在では国宝等の文化財として、城郭、公共施設などに使われるほか、室内用の小さなインテリア商品など多岐にわたり制作されています。
三州鬼瓦は、今日も瓦屋根の頂にそびえ、建物と人々の暮らしを見守っています。
- ※燻化:粘土の表面に炭素膜を形成させるための“いぶす”工程。

東京銀器とうきょうぎんき
経済産業大臣指定伝統的工芸品
東京都
銀器の歴史は古く、平安時代の法令集「延喜式(えんきしき)」の中に銀製食器や酒器の記述を見つけることができます。江戸元禄期の生活図解百科「人倫訓蒙図彙(じんりんきんもうずい)」には銀細工を専門とする「銀師(しろがねし)」が描かれています。
また、江戸中期の「徳川禁令考(とくがわきんれいこう)」ではかんざし、櫛、きせる等に金・銀の使用を禁じた御触れが出たことなどから、町人の間でも銀器、銀道具が広く使用されていたことがうかがえます。東京都が主要な産地となっており、唯一、国の伝統的工芸品に指定されています。
銀器は鍛金(たんきん)※1(打ち物)、彫金(ちょうきん)※2(彫刻)、鋳金(ちゅうきん)※3(鋳造)等の伝統的な技法により、純度1000分の925 以上の地金から器物、置物、装身具、日用雑貨などが作られます。
- ※1 鍛金:金属を板状,線状,立体状にたたきのばして器物を作る技法。
- ※2 彫金:たがね(金属を切断したり、彫ったり、削ったりするのに用いる工具)を使って金属を 彫ったり打ったりして模様を現す技法。
- ※3 鋳金:金属を溶かし、型に入れて、器や美術品を造る技法。

出石焼いずしやき
経済産業大臣指定伝統的工芸品
兵庫県豊岡市
出石焼の起源は3世紀後半の陶器製作から始まったと伝えられています。現代の白磁で知られる「出石焼」は、18世紀後半にその技術が三川内(みかわち)や有田から伝わり、磁器原料となる陶石(とうせき)が発見されたことで磁器焼成(じきしょうせい)※に成功しました。
19世紀には庶民の間で広く使われるようになり、明治時代に米国の万国博覧会で金賞を受賞するなど興隆期を迎えました。近年は、後継者難や原料不足など産地の置かれている環境は厳しくなっています。現在では、伝統技法を生かしながら現代にあった作品を制作している窯元(かまもと)に加え、多様な技法の焼き物に挑戦する若手作家も活躍しています。
出石焼は、白磁の色が冷たいほど白く、絵付けも繊細なタッチで落ち着いた色調を特色としており、磁器中の磁器と呼ばれ高い評価を得ております。
- ※焼成:焼き物など、乾燥後に高温に加熱して焼き固めること。

甲州印伝こうしゅういんでん
経済産業大臣指定伝統的工芸品
山梨県甲府市
甲州印伝は、江戸時代に上原勇七(うえはらゆうしち)が鹿革(しかがわ)に漆付けする独自の技法を創案し、町人文化を好む江戸の洒落者たちに愛され発展を遂げてきました。
鹿革はしなやかで丈夫なため、古来より藁(わら)を燻(いぶ)して染革(そめかわ)とする「燻技法(ふすべぎほう)」を使い武具や被服、袋物が作られてきました。勇七は、そこに実用性、装飾性を備えた漆を融合させ独自の革工芸として甲州印伝を生み出しました。
印伝の語源は17世紀、印度伝来の装飾革から印伝となったと伝えられています。後に和様化した装飾の鹿革のことを印伝と称し、江戸時代には各地で製造されていた記録があります。しかし現代では、甲州印伝だけが独自の技法を継承しています。燻技法(ふすべぎほう)、更紗技法(さらさぎほう)、漆技法(うるしぎほう)など四百年の伝統の技を継承しながら、時代を見据え、常に新しい甲州印伝づくりに挑み続けています。