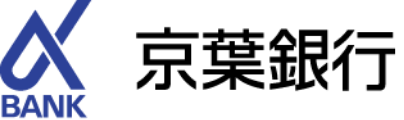ショーウィンドーギャラリー
2012年10月~2012年12月
「和の白」
日本の伝統-日本を詠う-
「和の白」
日本には色を表す伝統的な美しい名がたくさんあります。薄いピンク色は薄紅梅(うすこうばい)や桜色など春の花にたとえ、茶系の色は柿渋色(かきしぶいろ)や朽葉色(くちばいろ)といった秋を感じさせる名があります。
今回のテーマである「白」という色は古来より穢れ(けがれ)がない象徴であり、高貴な色として扱われてきました。しかし、自然の中には完璧な白はなく、少し黄が入っていたり青かったりしています。そのような微妙な色彩を細やかにとらえ、それぞれに名が付けられています。
今回は和紙、麻、漆(うるし)、灰、胡粉(ごふん)という異なる素材に見られる自然の白をご覧いただいています。どこか温かい色調が心を和ませてくれます。
記憶紙 和菓紙三昧きおくがみ わがしざんまい
和菓子の木型で和紙をかたどったアート作品は、千葉県佐倉市にアトリエを構える永田哲也氏によるものです。全国各地の菓子(かし)匠(しょう)の蔵を訪ね美しい型を探し出し、数々の作品を制作、発表しています。江戸時代から受け継がれてきた木型は、おめでたいもの、季節のものといった題材が多く見られます。その木型に白い手漉(てす)きの和紙をあて、長い年月を経た木型の持つ記憶ごと写し取る、ということから「記憶紙(きおくがみ)」と命名。美しく繊細な姿に日本文化の息づかいを感じます。

張子面はりこめん
室町時代に中国から伝来。江戸時代には全国へと普及し、各地で作らるようになった張子(はりこ)。特に城下町では不要になった紙が多く出回ったため、型へ何重にも和紙を重ね張りする張子産業が発展していったと言われています。ニカワと胡粉(ごふん)を練り合わせ、重ねた紙の上に塗りつけて白く固めます。胡粉は主に貝殻から作られ、日本画でも使われる白い塗料の一種です。展示品は姫路張子の面です。胡粉の土台の上に五穀(ごこく)豊穣(ほうじょう)祈願(きがん)の狐などが元気に描かれています。

灰はい
砂のように見える灰ですが、断熱作用があるにも関わらず、通気性に優れているため火のついた炭を灰の中に埋めても最後まで炭は燃え続けます。囲炉裏(いろり)や火鉢では夜、火のついた炭に灰をかぶせておけば上に紙が落ちたとしても燃え移りません。そして翌日掘り返すと灰の中からまだ火のついた炭が出てくるのです。くぬぎや楢を焼いて作られている灰は囲炉裏や火鉢に入れる他、あく抜きや陶器の釉薬(うわぐすり)にも使われています。

白漆しろうるし
「白(しろ)漆(うるし)」といっても真っ白な色をしているわけではありません。基本となる透明の茶褐色の漆(うるし)液(えき)に、二酸化チタニウムなどの顔料を混ぜ白色にします。しかし漆液の茶色が強く、「白漆」とはいうものの、塗り上げた色は白と茶の中間のベージュのような色になります。ところが使いこんでいくうちに、漆液の茶が抜け、少しずつ白さが感じられるようになります。年月とともに色の変化も楽しむことができる白漆の器。白くなるまで長く大切に使いたいものです。

麻布行灯あさぬのあんどん
麻は通気性に優れ、光沢があり、また水に濡れると強度も増すことから、服をはじめ帆や縄まで幅広く使われています。婚儀の結納の際には、白い麻糸の束が、するめや昆布などと一緒に用意されます。この束は「友(とも)白髪(しらが)」と呼ばれ、夫婦仲良く、共に白髪が生えるまで添い遂げられますようにという願いが麻の白い糸に込められたものです。麻布を使った行灯(あんどん)。麻糸が織り成す生成(きな)り色の布を通した柔らかな光は温かみがあふれています。