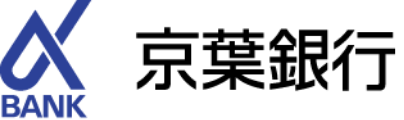ショーウィンドーギャラリー
2007年1月~2007年3月
「冬」
日本の伝統 「冬」
今年度は、暮らしの中の知恵に焦点をあてて、四季折々の知恵をご紹介しています。
今回は、「冬を乗り切るための知恵」にちなんだものをご覧いただきます。冬は凛とした美しさを持ちながらも、日々の暮らしには厳しい季節でもあります。そうした冬を乗り切るために、先人達が見つけた生活の知恵や工夫をご紹介します。
酒燗器しゅかんき
鍋で直接温めると味が変質することから、日本酒は必ず湯せんで温めます。屋外での酒席でもそれを遵守しようと、このような携帯用酒燗器が作られました。左のくぼみに炭を入れ火をおこし、右から本体内部へ水を入れ、炭の熱で湯を沸かします。その湯の中に酒を入れた銅製の器を入れ込んで待つこと数分…。屋外で、それほどの手間をかけた熱燗はさらにおいしいものでしょう。
細やかな表現を好む日本人は、熱燗も温度を5度刻みに分け、30度近くを日向燗、35度近くを人肌燗、ちょっと熱くなってきて50度であつ燗、55度以上では飛びきり燗という粋な名をつけています。

鉄瓶てつびん
鉄瓶の中でも南部鉄器のものが有名ですが、その歴史は江戸時代までさかのぼります。盛岡藩では良質の鉄を産出したことから、藩主南部利直が茶の湯釜を作ってみようと釜師を京から呼び寄せました。これが現在の南部鉄器のはじまりとされています。その後18世紀中頃、鉄瓶が作られるようになり、江戸後期に流行った歌舞伎の人気演目『源氏店』では「お鉄(鉄瓶のこと)は南部で…」というくだりが登場するほど、南部鉄瓶というブランドが確立されました。
現在では、鉄瓶で湯を沸かすと、湯の中に鉄分が出て健康に良い、また、その鉄分により茶の味も良くなるということから改めて実生活で使う道具として見直されています。

裂織さきおり
「裂織」は、その漢字が表しているように、裂いた布を織って作り上げたものです。
昔、木綿はとても貴重なもので、破れた衣服もはぎ合わせて使いました。それでもいよいよ使えなくなってしまった布を細く裂き、経糸(たていと)に麻を張り、緯糸(よこいと)にこの裂いた布を織り込んで「裂織」と呼ばれる布を作り上げたのです。その織目は非常に詰まっていて風を通さず、漁師たちや北国で愛用されました。
現在もその技は受け継がれ、古布を使った芸術として新たな命が吹き込まれています。今回は古い「裂織」と現代作家の手による新しい「裂織」を合わせて展示しています。
<特別出品 谷田部 郁子(やたべ いくこ)>
2002年 第1回 全国裂織展 入選
2003年 織成賞 第4回 現代に生きる手織物作品展 入選
2004年 第2回 全国裂織展審査員賞
2004年 第78回 国展 入選
2005年 第3回 全国裂織展 入選
2006年 第80回 国展 入選
たんたんと工房主宰(2001年~)
現在、松戸市を中心に作家活動、教室を展開されています。今回は本展示のために、寒色の古裂織と対する暖色の裂織作品を制作していただきました。

雪下駄ゆきげた
この雪下駄は、雪道に悩んだ元禄時代のお医者さんが考案したものです。高田藩(現在の新潟県上越市周辺)の御用医、細川春庵が、雪の坂道を上って登城しなければならず、工夫をこらしたのです。
下駄の歯は二本あると雪が挟まるので一本に。つるりと滑らないように、少し前傾に底を削り、体重が前にかかるようにします。鼻緒の止めは普通、裏側に出ていますが、裏に出ていると鼻緒が濡れて表まで水がしみてくるので、止めは下駄底を少しくり抜いたくぼみに納め、フタをし、水の浸入を防ぎます。さらに現在はつま先も濡れぬよう、カバーがつけられ、水をはじくオットセイの毛がつけられています。
<特別出品 竹田 亀治(たけだ かめじ)>
現在、日本で唯一の雪下駄職人と言われている新潟県在住の竹田さん。竹田さんの雪下駄は、伝統の逸品として上越市立総合博物館で展示をされたり、新聞などにも数多く紹介されていますが、職人として、人に履いてもらえる現役の雪下駄作りを続けています。
「私、下駄作りしかできませんから。」と語る竹田さんは、88歳になった今も尚、修行時代に親方が作ってくれたという道具を使い、毎日、心をこめて桐を削っています。

手焙りてあぶり
手元をあたためてくれる小さめの火鉢「手焙り」はお客さまと自分とそれぞれに配置するため、通常、対になっています。由緒ある大きな家には数十対にもなる手焙りが蔵からでてくることもあるそうです。
この小さな火鉢の中にも日本人は美学を求めました。灰の種類、きめの細かさにこだわり、そして寺社の庭で水を使わず、砂や石で山水を描こうとした枯山水の如く、この小さな火鉢の灰にもその美しさを追求したのです。「灰ならし」という歯のついたヘラのようなもので灰に地紋をつけ、波模様や、幾何学的な模様を描き出しひとつの世界を作り出したのです。細やかで、そして粋な心憎い演出です。