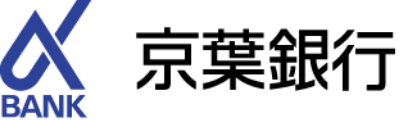


12/25
【初心者必見】将来、差がつく!?
「ドルコスト平均法」の鉄則をやさしく解説
【初心者必見】将来、差がつく!?
「ドルコスト平均法」の鉄則を
やさしく解説
資産形成

ホーム【初心者必見】将来、差がつく!?「ドルコスト平均法」の鉄則をやさしく解説
長期投資において、誰もが手軽に実践できる「勝ちパターン」として広く知られている、ドルコスト平均法。その有効性は多くの投資家に認められており、投資経験の差が影響しにくいことから、今から投資を始める方にもおすすめです。
しかし、どんなによい方法だとしても、投資にリスクは付きもの。メリットだけでなくリスクや注意点も理解し、ドルコスト平均法を味方につけましょう。
ドルコスト平均法とは?

株や投資信託などの金融商品には、当然ながら価格変動があります。その変動リスクを抑えるため、一度に大きな金額を投資するのではなく、毎月や毎週など定期的に一定額ずつ積立投資する方法が「ドルコスト平均法」です。金融商品の価格が高いとき、低いときの購入額の差を平均化できるのが特徴です。
これは、「分散投資」の考え方の1つ。分散投資というと「投資商品を複数にわける」ことをイメージするかもしれませんが、ドルコスト平均法のように、「投資のタイミングをわける」という時間軸の分散も有効なのです。
ドルコスト平均法のメリット
ドルコスト平均法のメリットは、長期にわたって一定額ずつ投資し続けることで、価格変動リスクを抑えられることです。
この「一定額ずつ投資し続ける」というのが最大のポイントで、結果的に投資対象の金融商品が安いときには多く買い、高いときには少なく買うことになります。価格下落のリスクはメリットに、同時に価格上昇時のリスクに対しては高値づかみ(価格が高いときに買ってしまって安くしか売れない状態)を防ぐ効果があります。
同じ金融商品への投資であっても、投資期間を長くして少しずつ買うことによって取得価格が平均化されるため、積立期間が長くなればなるほど価格変動による影響を受けにくく、リスクに強くなります。また、一定額ずつ購入することを決めているため、購入した商品の値動きを逐一確認しておく必要がなく、初心者にも始めやすい方法だといえるでしょう。
ちなみに、ドルコスト平均法の対極にある投資法は「一括集中投資」です。相場が安い時に一度に資金を投入し、高くなるのを待って売却すれば大きな利益が見込めますが、その見極めは容易ではありません。もし購入時の価格から下落すれば、一気に資産が目減りするリスクもあります。
ドルコスト平均法に向いている人
ドルコスト平均法による資産形成に向いている人は、どんな人でしょうか。3つの例を見てみましょう。
(1)時間を味方につけられる人
ドルコスト平均法は、長期で投資すればするほど購入価格を平均化できるメリットがあります。時間をかけることによってリスクを管理できるため、「時間がかかる」というより「時間を味方につける」と考えることができます。
現役世代の人で、将来を見据えて長期的な視野で資産形成を考えたい人など、投資期間に余裕がある場合は、ドルコスト平均法が向いているといえます。
(2)一度に多くの資金を用意できない人
一度に数百万円、数千万円といった金額を用意できない人も、ドルコスト平均法に向いています。なぜならドルコスト平均法は積立投資が基本であり、1回あたりの投資金額が数万円レベルからでも十分可能だからです。
(3)すぐに結果を求めない人
投資はお金を増やすための手法なので、どうしても一獲千金を夢見てしまいがちです。こうした夢を追い求める人には、ドルコスト平均法は物足りないかもしれません。しかし長期的な視野でコツコツと資産を増やしていくスタンスを持てる人であれば、ドルコスト平均法と合っているといえます。
ドルコスト平均法を始めるには
ドルコスト平均法を実践するのは、とてもかんたんです。運用対象となる金融商品を選び、それを毎月、毎週といった期間を決めて定期的に一定額ずつ購入し続けるだけです。
では、ドルコスト平均法に向いている商品にはどんなものがあるのでしょうか。株や外貨など、さまざまな選択肢がありますが、おすすめしたいのは「投資信託」です。
個別株の場合、せっかく積み立ててもその企業の業績が悪くなれば共倒れのリスクがありますが、投資信託は複数の株式などで構成されるため、リスク分散の効果があります。
また、種類が豊富で、幅広いラインナップから選ぶことができる点も投資信託のメリットです。たとえば、日本の日経平均株価、アメリカのS&P 500といった指数と連動した値動きをめざす「インデックス型」、指数を上回る値動きをめざす「アクティブ型」などがあり、自分に合った商品を選ぶことができるでしょう。少額投資非課税制度の「NISA制度」の活用もできるため、長期的な資産形成につながります。
どんな商品を選んだとしても、積立投資をするうえで重要なのは、対象となる金融商品の価格に関係なく「一定額ずつ購入」を遵守することです。これを守らないと、ドルコスト平均法の理論的根拠である“価格平均化”のメリットは得られないと考えましょう。
ドルコスト平均法を成功させるコツ
ドルコスト平均法のメリットを最大化し、成功させるためのコツは、主に以下の4つです。
(1)相場の動きに一喜一憂しない
価格の変動がある商品を購入し続ける投資方法なので、目先の価格変動に一喜一憂しないようにしましょう。よくあるのは少し利益が出たところで売ってしまい、投資を終わらせてしまうパターン。人間の心理として、目先の利益を獲得したい気持ちはよくわかりますが、「時間を味方につける」ことがドルコスト平均法の前提であることを忘れずに。
「続ける」ことが一番のパワーになるので、できるだけ相場を見ずに、将来を楽しみにするくらいの気持ちで機械的に買い続けるのがよいでしょう。
(2)自動積立機能の活用を検討する
先ほど、機械的に買い続けることがドルコスト平均法の基本であると説明しました。手作業だとどうしても相場を見てしまい、あれこれ考えてしまうのが人情です。そこで、可能であれば最初に設定をして、自動的に一定額ずつ購入し続けるサービスを利用することをおすすめします。銀行や証券会社には投資信託の自動積立サービスがあるので、検討してみましょう。
(3)右肩下がりの商品に注意
ドルコスト平均法は、購入価格を平均化してリスクを抑える方法です。購入価格の波が平均化されたとしても、相場の展開によってはダメージを受けることもあります。
たとえば、長期的に見て価格が右肩上がりになっている商品、レンジ相場といって一定の範囲内を往来しているような商品であれば、ドルコスト平均法が有効です。しかし、長期間にわたって右肩下がりの商品では、購入価格の平均化がうまく機能しません。
ドルコスト平均法を実践するときには、長期間で見たときに右肩上がりの価格推移が続いている商品を選ぶとよいでしょう。
(4)「やめどき」を見極める
どんなに長期間の投資であっても、いつかは終了し、利益を確定させるときがきます。ドルコスト平均法を続けていくと購入価格が平均化されていきますが、いつやめるかによって最終収支が決まるため、終了時の価格によってはマイナスになってしまうリスクがあります。
あらかじめ年数を決めておいて、その年数満了で新規積立を終了し、以後は積み立てた資産を原資に安定運用を行うというやり方もあるでしょう。また、「資産形成の目標額を達成したらやめる」という戦略も考えられます。ただ漫然と続けるのではなく、プラス収支で終了するための出口戦略を最初に描いておきましょう。
まとめ:ドルコスト平均法は「長期投資でコツコツ」がカギ

ドルコスト平均法は、投資の「勝ちパターン」といわれます。ただしそれは、長期投資で一定額をコツコツ積み立て、時間を味方につけられた場合。積立期間中は目先の値動きに惑わされず、10年後、20年後の自分のためであることを意識しながら、機械的に続けていくことが成功の秘訣です。
銀行などに相談すれば、あなたの目的と状況に合わせたアドバイスも受けられます。ドルコスト平均法のメリットを最大限に得られるよう、最初の戦略をしっかりと立ててから運用を始めましょう。