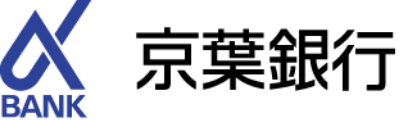


6/25
年金を受けとる前に
知っておきたいこと7選
ライフイベント

ホーム年金を受けとる前に知っておきたいこと7選
20歳以上のすべての人が関わる年金。当たり前のように保険料を支払っていますが、実はその制度や仕組みについて100%理解している人はそう多くありません。いざ年金をもらうときになって「こんなはずじゃなかった」と慌てないためにも、年金をもらう前に知っておきたい最低限のことを学んでおきましょう。
1:そもそも年金のしくみって?
年金制度とは、現役世代が支払った保険料を高齢者などの給付に充てる、世代間の支え合いの考え方を元に作られた制度です。高齢になって働けなくなったときのほか、障がいや死亡などのリスクに対処し、生活を支える仕組みになっています。
年金と言われるものには大きく分けて「公的年金」と「私的年金」があります。
公的年金とは
公的年金は、国が運営する年金制度全体のことを指します。公的年金には「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金」の2種類があります。
- 国民年金(基礎年金):20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する年金。
- 厚生年金:会社員・公務員が加入する年金。国民年金に上乗せするため、国民年金だけに加入している人よりも、将来もらえる金額が多くなる。
また、年金制度は「老齢年金」、「障害年金」、「遺族年金」の3種類に分けられます。一般に年金は高齢になってから給付を受けるものと思われがちですが、以下のような場合に受給できます。
- 老齢年金:原則65歳※に達した人が受け取る年金
- 障害年金:病気やケガなどにより、障害認定を受けた人が受け取る年金
- 遺族年金:被保険者が亡くなった場合に、生計を維持されていた遺族が受け取る年金
- ※ 性別・生年月日により受給開始年齢が異なる場合があります。
私的年金とは
私的年金とは、公的年金に上乗せして受け取ることができる年金のことです。企業などに勤めている人は、企業単位の年金として以下の制度が用意されていることがあります。
- 確定給付企業年金
- 企業型確定拠出年金
- 厚生年金基金
また、個人が自分で加入して積み立てる私的年金もあります。
- 国民年金基金
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 年金保険
会社員の方は、勤めている企業がどのような企業年金を実施しているかを確認してみましょう。企業年金の制度がない場合、自営業やフリーランスの方の場合は、個人年金を用意しておくと安心です。なかでも「個人型確定拠出年金(iDeCo)」は、自分で運用商品や金額を決めて資産形成を行うことができ、税制優遇も受けられることから、近年注目されています。
2:結局、いつからもらえるの?

国民年金の場合、保険料の納付義務は20歳以上60歳未満の40年間(480カ月)です。このうち10年間(120カ月)以上の納付があれば年金(老齢基礎年金)を受給できます。老齢基礎年金の受給開始年齢は原則65歳からですが、65歳以降に受給資格期間を満たした場合は、その時点からの支給となります。
厚生年金は段階的に65歳支給に引き上げられた経緯があり、男性は昭和36年4月2日生まれ以降、女性は昭和41年4月2日生まれ以降の人は65歳より支給されることになります。このように、老齢厚生年金の受給開始年齢は性別と生年月日により決まります。
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望により繰り上げ受給(60歳~)が可能です。ただしその場合、月々の年金額が0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは減額率0.5%)ずつ減額されます。同様に繰り下げ受給(66歳~)の請求も可能で、その場合は月々の年金額が0.7%ずつ増額されます。
3:ねんきん定期便はチェックしておくべき?
毎年誕生月に、ご自身の年金記録を記載した「ねんきん定期便」が送付されます。通常ははがき形式ですが、35歳・45歳・59歳時には封書で詳しい情報が送られてくるので、記載された年金加入記録について「もれ」や「誤り」がないか必ずチェックしましょう。
ねんきん定期便のほか、「ねんきんネット」に登録すれば、パソコンやスマートフォンからいつでも年金の状況を確認でき、将来受け取る老齢年金の試算ができます。また、厚生労働省ホームページ内「公的年金シミュレーター」を使えば、登録なしで将来の年金額試算が可能。ねんきん定期便を参照すれば入力が簡単に済むので、捨ててしまわずに手元に置いておくと便利です。
4:配偶者がいると年金額が増えるって本当?

厚生年金には、厚生年金の受給資格のある人が65歳になった時点で生計を維持している配偶者や子どもがいる場合、支給額が加算される「加給年金」という仕組みがあります。加給年金を受け取るためには、受給者の厚生年金加入期間が20年以上、受給者が65歳に到達した時点で65歳未満の配偶者がいる、もしくは18歳到達年度の末日まで、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子どもがいることなどの条件があります。
また、配偶者を対象とする加給年金は、配偶者が65歳になると停止されます。以降は配偶者自身が受け取る年金に振替加算が追加されることになっています。なお、振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた人に限られます。
5:年金をもらいながら働くことはできる?
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、給与収入がある場合でも受け取ることができます。「在職老齢年金制度」により、年金をもらいながら働いて収入を得られます。
ただし、企業などに勤めながら老齢厚生年金を受け取ると、給与に応じて年金額が減額されてしまいます。65歳以降に満額の年金を受給しながら働くためには、「給与収入と老齢厚生年金の受給額合計が月額51万円以下」もしくは「パート※や業務委託、フリーランスなど、厚生年金に加入しない方法で働く」必要があります。
- ※ パート勤務でも、一定の条件を満たすと厚生年金に加入することがあります。その場合、在職老齢年金制度の対象となり、給与によっては年金の一部が減額されることがあります。
なお、老齢年金の受給権発生後も、70歳まで厚生年金に加入することが可能です。厚生年金に加入した期間は、在職定時改定・退職改定により年金額の計算の基礎となる被保険者期間に追加され、70歳以降に受け取る年金額が増えることも覚えておきましょう。
6:万が一死亡したとき、配偶者の年金はどうなるの?
厚生年金の受給資格のある人(夫)が亡くなったときは、配偶者(妻)に寡婦年金や遺族年金が支給されます。支給内容は、年金加入状況や遺族の年齢によって異なります。下記は一例です。
-
自営業の場合:(子どもがいない)寡婦年金もしくは死亡一時金
(子どもがいる)遺族基礎年金 -
会社員の場合:(子どもがいない)遺族厚生年金
(子どもがいる)遺族基礎年金・遺族厚生年金
寡婦年金は、国民年金を10年以上納付した人(夫)が何の年金も受給せずに死亡したとき、その人が受けるはずだった老齢基礎年金の3/4を妻(婚姻期間10年以上)が60~64歳までの間、支給するものです。
一方、遺族基礎年金の支給対象は「子がいる配偶者」または「子」で、子が18歳になった年度末まで支給されます。また、遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた人(故人と生計を同じくし、年収850万円未満の人※)に支給されるもので、支給金額は老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4となっています。たとえば妻が遺族厚生年金を受け取る場合、60歳~65歳までは妻自身の老齢厚生年金または遺族厚生年金のいずれかを選択し、65歳以降は両方受け取ることができます。
- ※ ①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の順。夫、父母、祖父母が受け取る場合、死亡時において55歳以上であることが条件で、支給開始は60歳から。
7:年金のこと、誰に相談したらいい?

誰しもが関わっている年金制度ですが、その仕組みはかなり複雑で、自分で調べるのはなかなか難しいもの。そんなときは、お金のプロに相談してみるという選択肢もあります。FPなどに依頼することもできますし、行政や金融機関などで年金に関する無料相談会を開催していることもあるので、気になったらチェックしてみては。京葉銀行では、各店で無料年金相談会を定期的に実施しています。普段使っているお近くの銀行なら、気軽に相談できますね。
早速相談してみよう
年金だけに頼らない。自分で作る老後資産のすすめ
定年後の生活には、意外とお金がかかるもの。旅行に行ったり趣味を楽しんだりするほか、自宅の修繕費や医療費も確保しておかなければなりません。「退職金があるから大丈夫」と思っていても、まとまったお金は思っていたよりも早く減っていってしまうものです。さらに昨今の物価高を受け、生活費は増加傾向です。
「年金だけでは心許ないけれど、いつまで働けるか不安……」と感じる方も多いでしょう。老後を安心して過ごすためには、年金制度をしっかり理解し、健康の維持に努めることと同時に、いざというときに頼れる「老後資産」を作っておくのがおすすめです。NISA制度をはじめ、個人が資産運用に参入しやすい環境が整いつつある今、投資によって資産を増やすことはもはや必須ともいえるマネー戦略の1つ。少しでも早いうちから積み立てておけば、リスクを抑えながらメリットを得やすくなります。投資初心者の鉄則である「長期・積立・分散」を意識しながら、月々の余剰金や退職金などを活用した資産運用を考えてみてはいかがでしょうか。
年金のモヤモヤ、早めに解消しておきましょう

年金受給を前に、疑問や不安が生じる人は少なくありません。これまで払ってきた年金をどのように受け取れるのかがわかれば、セカンドライフのプランも立てやすいですね。子どもたちに負担をかけずに第2の人生を楽しむためにも、年金を含めたお金のモヤモヤを早めに払拭しておきましょう。年金のこと、資産のこと、退職後のマネープランのことなど、迷ったらぜひお近くの銀行を頼ってみてください。
相談会開催中
窓口で相談するなら
(厚生労働省HP)